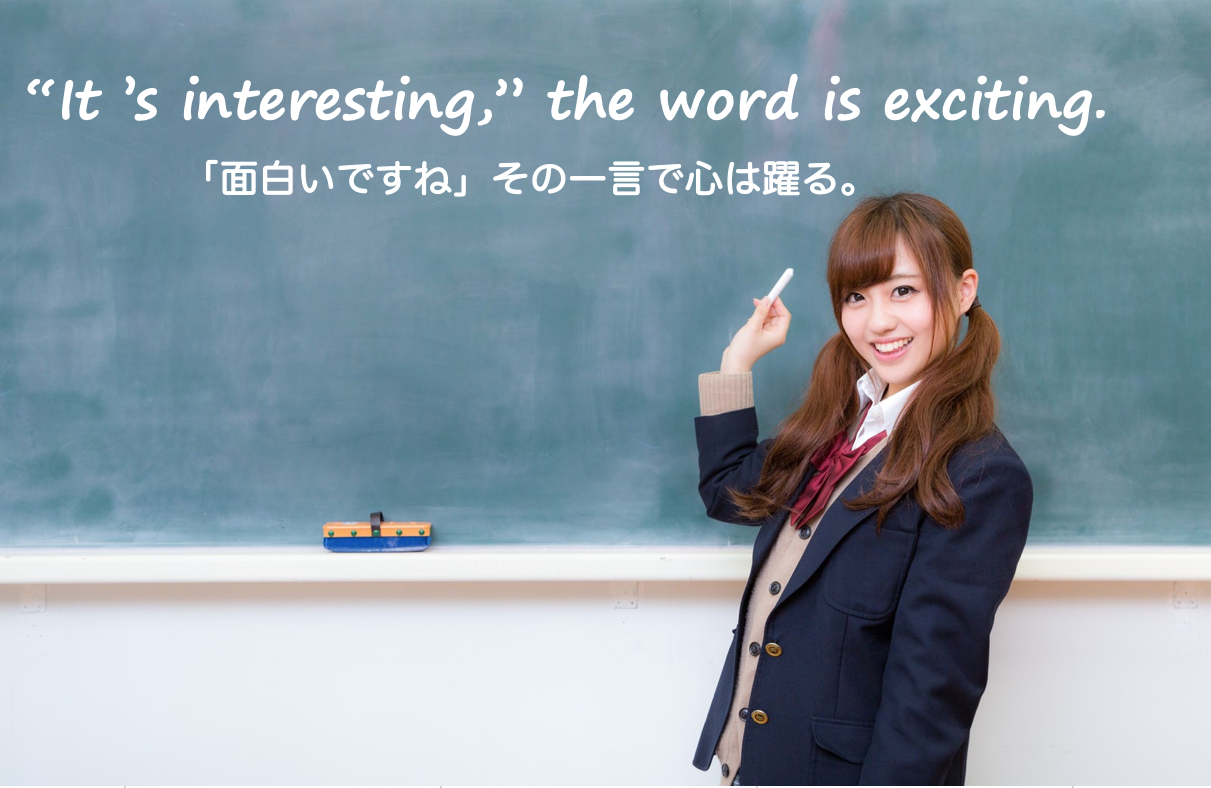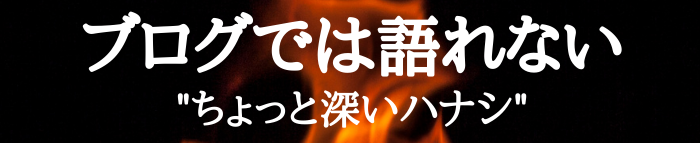今回は「周りから『面白い人』思われるためにはどうすればいいか?」というテーマで、
やるべき言動・やってはいけないことなどを具体的に解説していきます。
いきなり結論を言うと
【モテる面白さ】とは日常の発言や行動から作られるもの
です。
もし、万人ウケするお笑いネタやモノマネのレパートリーが必要だと思ったなら、安心してください。
そんなものは全くもって必要ありません。
これを踏まえここでは
- 面白い人に共通する言動や特徴
- 面白い人になるために今すぐ始められる方法と普段の意識作り
- 面白い人になりたいならやってはいけないNGな言動
を具体的にガチ解説していきますので是非ご覧ください。
※女性にモテたい男性は
【超重要】モテる男の性格「プレイフルネス」ってどんな能力?
も参考になるのでぜひご覧ください^^
Contents
スポンサードサーチ
会話や行動が面白い人に共通する特徴6つ【理由も】

さて、ここでは会話や行動が面白い人に共通する特徴6つを紹介していきます。
- 素直
- 聞き上手で話の広げ方が上手い
- 語彙力が豊富
- 興味や探究心が人一倍強い
- 恥を恐れない
- 雑学や時事ネタに詳しい
ユーモアがある人はあらゆるシーンでこれら能力を発揮しています。
理由も含め具体的に見ていきましょう。
面白い人の特徴1
素直
一緒にいて面白いと言われる人は共通して素直な人ばかりです。
あなたは恥ずかしい事や過去の失敗話を相談された時「自分も腹割って話そう」って気持ちになりますよね。
そうすると必然的に「居心地が良い」と感じやすくなるんですね。
逆に何を言われても強がったり上から目線で話したりすると相手からは
- プライドが高くて面倒くさい
- 頑固で話しづらい
大抵こんな感じのマイナス印象を持たれがちです。
特に合コンなど初対面相手が集う場だとこういうタイプは即残念な人認定されます。
素直さは「面白さ」以前の「話しやすい」印象を与えるための必要不可欠な要素です。
面白い人の特徴2
聞き上手で話の広げ方が上手い
面白い人は聞き上手で、相手から振られた話の広げ方も優れています。
聞き上手なことで相手の気持ちを満たされるため
「この人は話しやすい」→「この人の話は面白い」
という印象に繋がりやすいのです。
以下はマイナビが働く女性を対象に実施した調査結果です。
Q.【働く女性に聞きます】話が面白い人に共通する特徴は?
●第1位/「他人の話をよく聞いている」……49.7%
○第2位/「フレンドリーな性格」……46.3%
●第3位/「気配りができる」……40.4%
○第4位/「友だちが多い」……36.0%
引用元:マイナビウーマン
女性は安定したインプット&アウトプットができる男性に対して高評価をつけることが分かります。
例えば、アンケート結果1位は「他人の話をよく聞いている」となっています。
これ普通に考えたら誰でもできることですよね。
細かく見れば「聞き方が面白い」「リアクションが秀逸」などありそうですが、それならそういう答えがランクインするはずです。
にも関わらず「話を聞く」行為が1位なのは、話を聞いたその先に相手を満足させるアウトプットがあるからなのです。
おもしろい人が聞き上手なのは当たり前というわけですね。
面白い人の特徴3
語彙力が豊富
面白い人は語彙力が豊富です。
語彙力とは言葉・単語の知識量とそのアウトプット力のことです。
語彙力が豊富な人は同じ出来事でも幅広い表現方法で相手に伝えることができます。
同じ意味の内容でも単語や言い回しを変化させることで周囲を笑わせる、または場を盛り上げるといったことも可能です。
具体的な違いについては、簡単な文章例で見てみましょう。
例1:これまでの人生を振り返る時の表現方法
▼一般的な表現
「悪い事は一度もしたことがない」
▼応用的な表現
「真っ当に生きてきた」
「悪事に手を染めてはいない」
「ダークサイドに堕ちたことはない」
例2:絶景を見た時の表現例
▼一般的な表現
「とても綺麗な景色で感動した」
▼応用的な表現
「圧巻の景色だった」
「あまりの光景に目を疑った」
「感動を隠せなかった」
ここで挙げた簡単な文章だけでも赤字部分のように異なる単語を使った言い換えが可能です。
※言語表現のすごいところは時代や世代が生んだ造語などがどんどん誕生するという点です。
これらを駆使すれば、表現の種類はほぼ無限に作り出すことが可能です。
語彙力が優れている人はこんな感じでフレーズを選び組み合わせ、ごく普通の話を面白可笑しく表現しているのです。
面白い人の特徴4
興味や探究心が人一倍強い
発言や行動が面白い人は決まって自分以外に対して探究心が強いです。
まず、面白い人になるためには面白い発言や行動ができなければいけません。
そして面白い発言や行動をするためには元となるネタが必要になります。
なんなら常日頃から
「この人(物)の面白い点はどこか」
「どうすれば会話が盛り上がるできるか」
と考えるている人もいるくらいです。(僕です)
特に人を笑わせることが仕事のお笑い芸人さんや落語家さんなんかは
24時間365日この意識を持っているはずです。
プロ、素人に関わらず、どんな人であれ、
積極的な探究心なしにボケのセンスが鍛えられることはありません。
面白い人の特徴5
恥を恐れない
失敗や恥ずかしさを恐れずに発言や行動できるという点も面白い人に多い特徴の1つです。
人間誰しも失敗や恥をかくことは避けたいと思うはずです。
しかし人を笑わせる能力が高い人は、基本こういったことは気にしません。
なんなら、マイナス要素さえも面白さの糧と考える人が多いです。
思ったように人を笑わせられないとすれば原因の大半はまさにこの部分と言ってもいいでしょう。
真に面白い人は
【笑いが生まれるならダメな自分なぞいくらでも見せられる】
という人ばかりです。
素の自分を正直に見せられないと、どんなに努力したとしても面白さの質はある程度のレベルまでしか上がらないんですよね。
ただただバカになればいいわけではないものの、高すぎるプライドは「面白さ」の敵です。
例えば、お笑い芸人を思い浮かべてみてください。
バラエティ番組など、司会者との掛け合いで
【自分たちの恥ずかしいエピソードで周囲の笑いを誘うパターン】
ってありますよね。
もちろんこれはプロアマは関係なく、私達がやったとしても笑いを起こせるテクニックです。
過去の失敗談や恥ずかしい経験などをオープンに話せる人に対しては、その分相手も心を許しやすくなります。
結果、「一緒にいて楽しい」「面白い」といった印象を抱かれやすいのです。
面白い人に共通する特徴6
雑学や時事ネタに詳しい
面白い人は常に世の中にアンテナを張っており雑学や時事ネタなどの情報に詳しい人が多いです。
トレンドに敏感なので相手からどんな話を振られても柔軟に対応できるわけですね。
ここで再度マイナビウーマン調査のアンケートを見てみましょう。
Q.【働く女性に聞きます】話が面白い人に共通する特徴は?
●第5位/「ボキャブラリーが多い」……32.3%
○第6位/「好奇心旺盛」……31.7%
●第7位/「ニュースに敏感」……29.8%
○第8位/「趣味が幅広い」……27.6%
●第9位/「人が好き」……26.4%
○第10位/「さまざまな年齢の友人がいる」……23.3%
引用元:マイナビウーマン
※1位~4位は【面白い人に共通する特徴2】にて確認可能です。
ボキャブラリー(=語彙力)や好奇心は雑学力と直接的は繋がらないものの、情報の知識量が多いほど活かされるスキルです。
常日頃から様々な情報を意識して生活しているからこそネタが尽きない話上手になれるわけですね。
【重要】面白い人になるために意識すべきこと7つ

モテる面白い人になるために意識すべき事は以下の7つです。
- 面白いと感じた人の言動を真似する
- バラエティ番組を見る
- 語彙力を鍛える(多くの言葉を知る)
- 人と交流できる場所に積極的に出向く
- 自分のターンで会話を終わらせない(でも無理はしない)
- 目につく物を話のネタにする
- 話題に合わせて感情表現も忘れずに
ここで紹介する内容は普段の生活で1人でもできることばかりです。
しっかり学んで活かしてみてくださいね。
日常意識1
面白いと感じた人の言動を真似する
日頃から「この人面白い!」と感じた人がいたらその言動を真似するようにしましょう。
最初は恥ずかしいと思うかもしれませんが非常に大事です。
なぜなら、笑いを誘う面白い言葉や行動というものは万人に通じるものだからです。
あなたが「この人の話し方面白いな」と感じれば
大抵はあなた以外の人でも見ても同じ感情を抱きます。
お笑い芸人の漫才シーンなどを思い浮かべてみてください。
1つのネタを披露して多くの人の笑いを誘っていますよね?
芸人さんが人を笑わせるプロだからという部分はあまり関係ありません。
私たち人間誰しも笑いのボーダーラインに大きな違いなどないのです。
身近な人でも芸能人でも、面白いと感じる部分があれば、その人の「何がどう面白かったのか?」を気にする癖をつけましょう。
慣れないうちは丸々コピーしても構わないので、人の面白かったネタを他の人に試してみてください。
慣れてきたら少し言い回しを変えたり自分流にアレンジを加えたりしてみましょう。
面白い人の言動を真似することで最終的には自分に合った言い換えや言い回しが身についていきます。
日常意識2
バラエティ番組でトーク術を学ぶ
バラエティ番組からトーク術や表現方法を学ぶことは非常に効果的です。
バラエティ番組は面白い人たちの総本山です。
「人を笑わせる面白さ」について大事なテクニックを一気に学ぶことができます。
話の内容、声色、間のとり方など、どんな話をどのようにすればウケるのかを見聞きして自分に活かすようにしましょう。
特におすすめはMCが存在して複数の人たちを相手にトークを展開するタイプの番組です。
このタイプのバラエティ番組には
【MCのトークや話の振り方で大勢の人を盛り上げる】
という構図に笑いを生み出すエッセンスが数多く詰まっており、表現、間、話のフリ方などを効率よく学べます。
参考までに、個人的におすすめの番組をご紹介させていただきますね。
- 踊る!さんま御殿(日本テレビ:火曜19時55分~)
- ほんまでっか!?TV(フジテレビ:水曜21時~)
- ワイドナショー(フジテレビ:日曜10時~)
- 行列のできる法律相談所(日本テレビ:日曜21時~)
特に明石家さんまさん、東野幸治さんあたりの仕切り力やトーク技術は何度見ても勉強になります。
上記以外でも気に入った(できるだけMCがいる)バラエティ番組があればOKです。
出演者のやりとりをじっくり見てみましょう。
最初のうちは「さっきのトーク面白かった」「この掛け合い笑える」レベル感で問題ありません。
喋りが面白いと思う芸人やタレントの技を研究する癖をつけてください。
話を振る側と受ける側の言動を一度に勉強できるバラエティ番組は面白い人になる上で非常に効果的な練習材料です。
日常意識3
語彙力を鍛える(多くの言葉を知る)
面白い人になるためには語彙力を鍛えることが絶対不可欠です。
常日頃から欠かさないようにしましょう。
語彙力とは
【どれだけの言葉を知っていて、かつ巧みに使いこなせるか】
の力を表す言葉です。
語彙力がある人だと普通の言葉でもフレーズや言い回しを変えて面白可笑しく表現することが可能です。
例えば、ある事柄を表現する時に自分は1種類の言葉しか知らないとします。
その言葉が誰が聞いても面白いと思わないフレーズなら、当然で人を笑わせることはできませんよね。
しかし、同じ意味を表す類似言語を3つでも4つでも知っていれば、別の表現や組み合わせで相手に伝える事ができます。
仮に「面白い」という言葉で考えてみると、
- 笑える
- 爆笑する
- ウケる
- 腹筋崩壊した
- 笑い死にする
- 興味深い
- 愉快な
ちょっと考えただけでこれらの言葉が思いつきました。
たった1つの単語でも語彙力が増すことで表現の幅は一気に広がります。
この中に相手の感情を動かす言葉が含まれている可能性があります。
語彙力がどれだけ高いかでその人の面白さが決まるといっても間違いではありません。
日常意識4
人と交流できる場所へ積極的に出向く
面白い人になるために人と交流できそうな場所に行くということも意識づけましょう。
テレビ番組を見て勉強したり語彙力を鍛えることも大切です。
また、合わせて実践を積むこともスキルアップに繋がります。
加えて生のコミュニケーションに触れることで想定外の状況に対して臨機応変に対応する練習にもなります。
ある程度自信がついたら積極的に現場での交流を重ねていきましょう。
- 友達や会社の飲み会に参加する
- ネットのオフ会やイベントサイト
- 合コンや街コン
これらに参加してみるのもありです。
例えば立ち呑み屋やバーなどは隣同士で会話することも多く雑談の練習ができます。
(僕も最初は週4で近所の立ち呑み屋に通ってトーク練習をしました。笑)
机上の勉強も大事ですが、なんだかんだ言って場数に勝るものはありません。
会話力に自信がついたら実践の場で活かすことで俄然成長スピードが早まりますよ^^
面白い人になるための意識5
自分のターンで会話を終わらせない(でも無理はしない)
誰かが自分に話を振ってきた時はなるべく自分で話を終わらせない癖をつけましょう。
繰り返しになりますが面白い人になるためには「普通の話を面白く伝えられる」能力が必須です。
相手から振られた話を自分で終わらせてしまっては面白い返答をするチャンスを逃してしまいます。
もちろん最初は返答がおぼつかなくても全然よくて、
【誰かに話を振られた際に自分から言葉を発する習慣をつける】
ということが大切です。
ちなみにコミュニケーションに関する心理学の1つにメラビアンの法則というものがあります。
メラビアンの法則
感情や態度について矛盾したメッセージが発せられたときの人の受けとめ方について、人の行動が他人にどのように影響を及ぼすかというと、話の内容などの言語情報が7%、口調や話の早さなどの聴覚情報が38%、見た目などの視覚情報が55%の割合であった。この割合から「7-38-55のルール」とも言われる。
引用元:Wikipedia「メラビアンの法則」
この法則によれば人は相手の印象を
言語情報を7%、聴覚情報を38%、視覚情報を55%
の割合で認識するとあります。
言語情報はここでは会話の内容にあたりますね。
つまり、人は会話の内容よりも話の量や会話に対する姿勢の方が印象に残りやすいということなのですね。
もっと言えば内容どうこうよりも「どれだけ楽しませようとしてくれたか?」を見ていることになります。
話を振られた時は面白い返しをするチャンスだと認識し、しっかり投げ返す意識をつけましょう。
面白い人になるための意識6
目につく物を話のネタにする
話を盛り上げる訓練として、周囲の目についたものをネタにしたトークを練習してみましょう。
目に入るものはネタの宝庫です。
目の前の物から話を広げるテクニックが身につけば話題ゼロの状態から話を盛り上げる事はさほど難しくありません。
例えば、飲みの席であればその場にある物(名前、形状、雰囲気、動きetc)を探してみてください。
特にメニュー表なんかはネタ帳みたいなもんなのでおすすめです。
※珍しい名前の料理、初めて見るような料理の写真などどこからでも話題を広げることができますからね^^
店内の置物や流れている音楽など「これ面白いな」と感じる物であれば何でもいいのでネタになるか考えてみましょう。
お分かりのように、この練習は場所を問いません。
目につくものを話しのネタにする練習は1人でもできることです。
通勤通学時など日頃から身の回りのものをネタにして話をする練習をしてみてくださいね。
面白い人になるための意識7
話題に合わせて感情表現も忘れない
会話の面白さを引き立てるのに感情表現は欠かせません。
感情表現のない会話は相手に真意が伝わりづらいからです。
最悪の場合、相手から「つまらない奴」と思われてしまうかもしれません。
無理やり喜怒哀楽を表現する必要はありませんが、表情や声に気持ちを込めて受け答えした方が話のインパクトは断然上がります。
(こういう点をしっかり意識できるかできないかは相手が感じる印象において大きな差に繋がりますよ)
もちろんこれは文章でのやりとりでも同じです。
例えば以下を見てください。

なんとそれ2回とも同じ友達だったんだよね。
これでも話は伝わりますが、抑揚表現が全くないため文章で見ても驚いたのかなんなのか全く分かりません。
一方で、同じ文章に感情表現を付加するとどうでしょうか。

その相手がなんと・・・2回とも同じ友達だったんだよね!笑
めちゃくちゃ驚いて思わず「えっ!?」て大声出しちゃったよ!!
同じ文章でもこちらの方が
その体験をした時の気持ちや感情の起伏がかなり鮮明に伝わりますよね。
印象に関する心理学の1つに【初頭効果】というものがあります。
心理学者アッシュ氏の実験によって提唱された
「人は初対面時に示された情報が最も印象に残りやすく、その後の人物像の形成に大きく影響する」
という行動心理学です。
相手と初対面時に提示された印象(表情、態度、行動)で
「この人ってこういう人か」
とある程度位置づけられてしまうというわけですね。
会話の味付けとして感情表現は欠かせないアイテムといえます。
スポンサードサーチ
面白い人を目指すなら避けるべき言動5つ
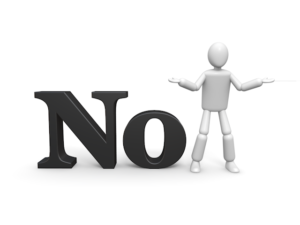
面白い人を目指すにあたりやってはいけない発言や行動は以下です。
- 自慢話が多い
- 無理に喋って盛り上げようとする
- 誰も知らない身内ネタで盛り上がる
- 長話(しかもオチなし)
- 否定から入る
1つずつ見ていきましょう。
避けるべき言動1
自慢話が多い
「この人マジうざぁ!」と思われやすい行為不動のNo.1といえば自慢話です。
自慢話はそもそも相手の「聞きたい」「知りたい」欲とは関係なく聞きたくもない話を押し付ける行為です。
基本、相手に良い印象を持たれることはありません。
マイナビさんの調査結果を見ても格の違いが分かります。
▼女子にモテない「つまらない男」の会話
・「自分の自慢話は楽しそうに話すのに、こちらの話はあからさまに早く話終わってよ、オーラを出す男性」(32歳/運輸・倉庫/事務系専門職)
・「過去の武勇伝ばかり話す」(26歳/医薬品・化粧品/営業職)
・「まったく自分が入っていけない世界の話題を延々と続ける人」(26歳/金融・証券/事務系専門職)
・「こっちが一生懸命話していても、相槌だけでリアクションが薄い」(30歳/機械・精密機器/営業職)
・「すぐ『知らない』『やったことない』『興味ない』『わからない』と言う無気力無関心で物を知らない男、いわゆる引きこもり系?」(32歳/小売店/販売職・サービス系)
引用元:マイナビウーマン
自慢話がいかにNGかは世の声が全てを物語っていますね。笑
ただ、いかなる時も自慢話が絶対にNGかというと実はそういうわけでもありません。
例えば、相手がこちらのことを褒めている、
【つまり相手があなたをヨイショしているような状況】
であれば多少の自慢は問題ないでしょう。
相手が求めてもいない状況で自慢話をするのは危険なので避けましょう。
避けるべき言動2
無理に喋って盛り上げようとする
会話が途切れた時や沈黙時、無理に喋ったり極端なリアクションをする行為は結果的に自分の首を絞めることになり危険です。
こういう時は大抵、考える余裕がないのでぎこちない(つまらない)会話内容になりがちです。
こんな状態でスベろうもんなら「なんか必死だな〜笑」思われるかもしれません。
無理に喋って「必死でつまらない人」と認識されるのは絶対避けるべきです。
仮にそこで黙っていたとしても、つまらない人というより無口な人と思われる可能性の方が高いので。
「無口」はそこまで悪い印象ではありません。
会話内容を考える余裕がない時は焦らず、一度冷静になってから次のチャンスを探しましょう。
避けるべき言動3
誰も知らない身内ネタで盛り上がる
飲みの席などでついつい話しがちな身内ネタですが
相手にとって何のメリットもない会話ジャンルなので避けましょう。
なぜなら身内ネタは以下印象が強いからです。
- 他人からすると知らない事が多すぎて興味を持ちづらい
- 相手に疎外感を与えてしまう
複数人の飲みなどで一部の人達が知り合いだった場合は特に注意が必要です。
「そんな話知らねーし、よそでやれや。つまんねーヤツだな!」
なんて気持ちを抱かせること必死です。
会話のネタがなくなった時などは、つい身内ネタに走ってしまいがちですが、デメリットが多いので注意しましょう。
避けるべき言動4
長話(しかもオチがない)
飲みの場などで会話する時はダラダラと話が長くならないよう注意しましょう。
せっかく面白い話ができても話が長いと相手に真意が伝わりづらく、嫌悪感を抱かれる可能性が増してしまいます。
その上オチがなければもう最悪です。
ただもし相手がこちらに対して以下のような感情を抱いていればこの限りではありません。
- こちらの人間性や性格を尊敬している
- 絶大な信頼をおいてくれている
まあ初対面時ならなかなかあり得ないですよね。笑
相手に多少の理解があっても長話はメリットが少ないです。
日頃から気をつけてみてください。
避けるべき言動5
否定から入る
相手の話に「でも」や「俺なら」「私なら」のように
否定から入る癖があれば直すようにしましょう。
基本的に人が誰かに話を持ちかける理由は
「ただ話を聞いてほしい」「共感を求めている」の2種類です。
にも関わらずいきなり内容を否定されれば相手の機嫌が良くなるわけありません。
タイ料理が苦手と言っている相手に笑顔でパクチーをプレゼントするようなものです。
人間には承認欲求という本能的思考があります。
承認欲求
人間は他者を認識する能力を身につけ、社会生活を営んでいくうちに、「誰かから認められたい」という感情を抱くようになる場合が多い。この感情の総称を承認欲求という。
引用元:Wikipedia「承認欲求」
承認欲求は基本的に誰もが持つ本能的心理です。
あなたももし、のっけから話の本筋も聞かずに否定されたら「は?なんなの?」ってなりますよね?
どんなに自分と関係ない内容の話だとしてもいきなりの否定はイラつくものです。
相手が老若男女限らず、否定から入る会話は面白さどころか感情を逆撫でするのが目に見えているのでやめましょう。
【まとめ】ボキャブラリー要素はあなたの人生に付加価値を与える

周りから「面白い人」と思われることは、すなわち他人から興味を持たれているということです。
これって実はすごいことで、
仕事では人脈構築に役立ったり恋愛では女性の人気を総取りできたり
と人生を生きる上で強力なアドバンテージにする事が可能なんです。
では、ここまでの内容を復習してみましょう。
※赤文字は特に重要な要素
▼会話や行動が面白い人に共通する特徴は以下7つ
- 素直
- 聞き上手
- 豊富な語彙力
- 何にでも興味を持つ
- 恥を恐れない
- 雑学や時事ネタに詳しい
▼誰からもウケる鉄板の話題はあるの?
→ 基本的にないと思ってください。面白い人は「普通の話を面白可笑しく話す」ということをしています。
▼面白い人になるために意識すべきこと7つ
- 面白い人の言動や作り出す空気感を真似をする
- バラエティ番組でトーク術を学ぶ
- 語彙力を鍛える
- 人と接触できる場に行く
- 会話はできる限り自分ボールで終わらせない
- 目につくものをトークのネタにする
- 話題に合わせて感情表現も忘れない
▼面白い人を目指すなら避けたい5つの行動
- 不要な自慢話
- 無理に話を盛り上げようとする行為
- 誰も知らない身内ネタ
- オチなしの長話
- 否定から入る
▼会話力を鍛えるなら以下記事もぜひご一読ください
長くなりましたが、ここまで読んでいただきありがとうございました!